バルーン治療が始まった。
詳しい仕組みはわからなかったが、胃カメラの先にバルーンがついていて、狭くなった食道に空気を送り込むことで、内側から広げていくという治療だった。そういう説明を受けた。
手術にあたっては麻酔を使った。
といっても、全身麻酔や感覚がまったくなくなるようなものではなく、胃カメラでも使われるような「眠たくなる麻酔」だった。
最初は麻酔で眠ってしまったが、治療中、とてつもない苦しさで目が覚めた。
息が詰まるような感覚に襲われて、思わず体が強張った。
「追加の麻酔を入れます」
そう言われたあとのことはよく覚えていない。
気がついたときには、また眠っていた。
1回目の手術は無事に終わり、その後も何度かバルーン治療を受けた。
少しずつ、私は食事をとれるようになっていった。
久しぶりに食べるごはんに、心が躍った。
嬉しくなって、すぐに病院の売店であんこ入りのドーナツを買いに行ったことを覚えている。
それを食べようとしたとき、両親は心配そうな顔をしながらも、どこかほっとしたような、うれしそうな笑顔を浮かべていた。
「もう治らないかもしれない」
そんな不安に押しつぶされそうになった時期もあったけれど、私は無事に退院することができた。
ただ“日常生活に戻れる”というだけで、こんなに幸せを感じられるなんて思わなかった。
私はもともと好き嫌いが多い方で、ごはんを残すことにそれほど罪悪感もなかった。
でも、この経験を通して、“食べられる”ということが、どれほど当たり前ではないかを知った。
それからは、ごはんを残さないように意識するようになった。
そんな小さな気づきが、今の私を支えてくれている。
その後は通院を続けながら、治療を重ねていった。
最終的には、胃カメラのスコープ(約11〜12ミリ)が通るくらいまで広がれば治療は終了、という目安だった。
先生と相談しながら、少しずつそこを目指した。
ありがたいことに、学校にも復学できた。
本来なら出席日数が足りず進級できなかったはずだったが、先生たちの計らいで春休みに補習を受けることで、同級生と一緒に進級することができた。
部活にも復帰しようとしたが、治療を優先するために退部を考えていた。
顧問の先生に相談すると、「無理にやらなくてもいいから、マネージャーとしてでも在籍しておいで」と言ってくれた。
私は本当にたくさんの人に助けられていた。
支えられて、今ここにいるのだと思う。
でも——
治療が終わってからも、ベーチェット病という診断名は残り、薬は飲み続けていた。
定期的に通院もしながら、経過を見ていた。
けれど、私はずっと感じていた。
あの時、心から“ああ、治る”と感じたあの安らぎ。
何もかも認めて、受け入れて、心の澱がスーッと消えたような、あの感覚を私は信じたかった。
病院からは、ベーチェット病の難病認定を受けるよう勧められた。
高額な薬代が免除されるなどの制度があるためだ。
でも、私はどうしてもその手続きに踏み出せなかった。
難病と認定されたら、「私はベーチェット病なんだ」と、自分で認めてしまう気がした。
それは、将来どんな症状が出ても「おかしくない」と、自分に許可を出してしまうことのように思えた。
私は、診察のたびに数値にも異常が出ていないこと、ただ薬を飲んだというだけで病名を与えられたことに、どうしても納得がいかなかった。
だから、私は認定を受けることも、薬を飲み続けることも、やめた。
ある日の診察で、先生が私の体の状態を診て言った。
「調子は良いみたいだね。このまま薬は続けていこう」
私は言った。
「実は、薬…もう飲んでいません」
先生は驚き、そして厳しく言った。
「勝手にやめたら、症状が出るぞ。
目が見えなくなって失明しても、知らんからな」
私は、それでも言った。
「私は自分がベーチェット病だとは思っていません。
今後も、薬を飲むつもりはありません」
帰りの車の中、私は涙が止まらなかった。
こわかった。
先生に突き放されたような気がしたし、自分の決断が間違っていたのではないかと、心の奥が揺れた。
でも——
私の決意は変わらなかった。
私は、自分を“病人”として生きることは、もうしないと決めた。
私は、私として、生きていく。
19歳の春。
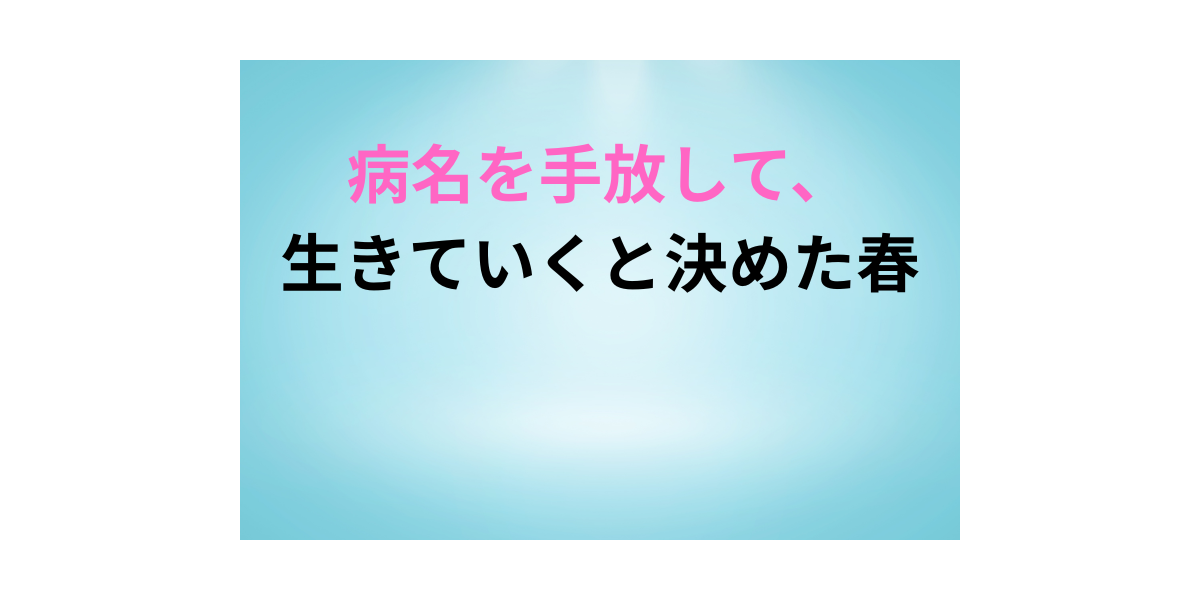


コメント